不動産を相続することになった際、多くの人が直面するのが「何をすればいいのか分からない」「費用がいくらかかるのか不安」といった手続き上の悩みです。特に相続登記や名義変更といった法的な手続きは、専門的な知識が必要となることが多く、放置すると相続トラブルの原因になるケースも少なくありません。
本記事では、不動産相続手続きを無料または低コストで進めるためのポイントや注意点を詳しく解説します。相続の予定がある方はもちろん、将来に備えて知識を身につけておきたい方にも役立つ情報をお届けします。
不動産の相続手続きが無料!?各専門家が勢ぞろいの新サービス!
\不動産相続のご相談は、クルーズカンパニーにお任せください/
不動産相続とは?よくある悩みと課題

不動産の相続は、他の財産の相続とは異なる特殊性があり、多くの人が様々な悩みや課題に直面します。
相続登記って何?
相続登記とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた不動産の名義を、その不動産を相続した方(相続人)の名義に変更する手続きのことです。正式には「相続による所有権移転登記」といいます。
手続きはなぜ必要?
- 所有権の公示
登記簿謄本(登記事項証明書)に名義を記載することで、その不動産の所有者が誰であるかを第三者に公示し、権利関係を明確にします。 - 権利の対抗力
相続登記をしないと、その不動産の所有権を第三者(例えば、その不動産を二重に売却しようとした者など)に対して主張することができません。 - 売却・担保設定
相続した不動産を売却したり、金融機関から担保に入れて融資を受けたりする場合、名義が相続人に変更されていることが必須となります。 - 2024年4月1日からの義務化
これまでは相続登記は任意でしたが、2024年4月1日からは相続登記が義務化されました。不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記申請をしなければ、10万円以下の過料が科される可能性があります。これにより、これまで放置されていた「所有者不明土地」問題の解消が期待されています。
なぜ手続きが複雑になるのか?
- 関係者の多さ
複数の相続人:兄弟姉妹、配偶者、甥姪など、相続人が複数いる場合、全員の同意や協力が必要になります。連絡を取り合ったり、意見を調整したりする手間が生じます。
利害関係の調整:各相続人の希望(不動産を所有したい、現金で分けたい、早く手続きを済ませたいなど)が異なるため、遺産分割協議が難航することがあります。
専門家の関与:状況によっては、弁護士、司法書士、税理士、行政書士など、複数の専門家との連携が必要になります。 - 必要書類の多さと複雑さ
戸籍謄本類:被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本などが必要です。これは、被相続人に隠し子や養子がいないかなどを確認し、漏れなく相続人を確定するために不可欠です。また、相続人全員の戸籍謄本も必要になります。これらの書類は、本籍地の役所でしか取得できず、郵送での請求も時間と手間がかかります。
住民票、印鑑証明書:相続人全員の住民票や印鑑証明書が必要です。
固定資産評価証明書:不動産の評価額を確認するために必要です。
遺産分割協議書:相続人全員で遺産をどのように分けるかを合意した書面で、実印の押印と印鑑証明書の添付が必要です。
遺言書:遺言書がある場合は、その内容が優先されますが、公正証書遺言以外は家庭裁判所での検認手続きが必要な場合があります。 - 専門的な知識の必要性
法律知識:民法上の相続の規定(法定相続分、遺留分、寄与分など)を理解している必要があります。
登記に関する知識:不動産登記法の規定に基づき、申請書の作成や添付書類の準備を行う必要があります。記載事項に不備があると補正を求められたり、却下されたりすることもあります。
税務知識:相続税の計算方法、控除、特例(小規模宅地等の特例など)について理解していないと、余計な税金を支払ってしまう可能性があります。
評価知識: 不動産の評価額を正確に算出するためには、専門的な知識が必要な場合があります。 - 手続きのタイムリミット
相続税の申告・納税:被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内。
相続登記:2024年4月1日以降は、不動産を相続したことを知った日から3年以内。
遺留分侵害額請求:相続開始と遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った日から1年以内、または相続開始から10年以内。 これらの期限があるため、焦りやプレッシャーを感じることもあります。 - 不動産特有の問題
分割の難しさ:現金や預貯金と異なり、不動産は物理的に分割することが困難なため、「共有」「換価分割」「代償分割」「現物分割」など、どの方法で分けるかを決めるのが難しい場合があります。
評価の変動:不動産の価格は経済状況や立地によって変動するため、相続発生時の評価額と実際に売却する際の価格が異なることがあります。
不動産の相続手続きの基本的な流れ

不動産の相続手続きについて、「遺産分割協議から登記までのステップ」に焦点を当てて説明します。
遺産分割協議から登記までのステップ
遺言書がない場合、または遺言書があっても遺産分割協議を行う必要がある場合(遺言書に記載のない財産がある場合など)は、以下のステップで進めます。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を全て取得し、法定相続人を確定します。
- 相続人全員に連絡を取り、相続手続きを進める旨を伝えます。
- 不動産、預貯金、有価証券などのプラスの財産と、借金などのマイナスの財産を全て洗い出します。
- 不動産については、固定資産税の納税通知書や固定資産評価証明書などを確認し、評価額の目安を把握します。
- 相続人全員で、どの財産を誰がどのように相続するか話し合います。
- 不動産については、
現物分割:不動産を特定の相続人が単独で取得する。
代償分割:不動産を取得する相続人が、他の相続人に現金などで代償金を支払う。
換価分割:不動産を売却し、その売却代金を相続人で分ける。
共有:不動産を相続人全員で共有名義にする。 などの方法があります。 - 全員の合意が必要です。一人でも反対する相続人がいれば、協議は成立しません。
- 話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停・審判を申し立てることもあります。
- 遺産分割協議がまとまったら、その内容を明記した「遺産分割協議書」を作成します。
- 協議書には、不動産の表示(所在地、地番、家屋番号、種類、構造、床面積など)と、誰が相続するのかを明確に記載します。
- 相続人全員が内容を確認し、署名・実印を押印します。全員の印鑑証明書を添付します。
- 遺産分割協議書やその他の必要書類を揃え、不動産の所在地を管轄する法務局に相続登記を申請します。
- 登記申請書を作成し、添付書類と共に提出します。
- 法務局で審査が行われ、問題がなければ登記が完了し、新しい名義の登記識別情報通知(権利証)が発行されます。
必要な書類一覧
不動産の相続登記に必要な主な書類は以下の通りです。ケースによって追加書類が必要となる場合があります。
- 相続登記申請書:法務局のウェブサイトからダウンロードできます。
- 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本を含む):これにより、法定相続人を確定します。
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票:被相続人の登記簿上の住所と死亡時の住所が異なる場合などに必要です。
- 相続人全員の戸籍謄本:現在の戸籍謄本で構いません。
- 相続人全員の住民票
- 相続人全員の印鑑証明書:遺産分割協議書に押印したものと同一の印鑑の証明書です。
- 遺産分割協議書:相続人全員が署名・実印を押印したもの。遺言書がある場合は不要ですが、遺言書の内容と異なる分割をする場合は、遺言書の写しと相続人全員の合意書が必要です。
- 不動産の固定資産評価証明書:登記申請年度のもの。市区町村役場で取得します。
- (遺言書がある場合)遺言書:公正証書遺言の場合は原本または謄本。自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認済証明書が必要です。
- (相続放棄した相続人がいる場合)相続放棄申述受理証明書
その他、状況に応じて必要となる書類の例
- 不在籍証明書、不在住証明書(相続人が行方不明の場合など)
- 不在籍証明書、不在住証明書
- 特別代理人選任審判書(未成年者がいる場合)
- 登記原因証明情報(遺産分割協議書がこれに該当します)
- 代理人によって申請する場合は、委任状
登記申請にかかる時間と費用の目安
かかる時間(期間)の目安
- 書類収集:1週間〜1ヶ月程度(戸籍謄本の郵送請求や、相続人の人数、本籍地が複数ある場合などによって大きく変動します)。
- 遺産分割協議:数週間〜数ヶ月(相続人の人数や関係性、財産の内容によって大きく異なります。意見対立がある場合は年単位になることもあります)。
- 登記申請書の作成・提出:数日〜1週間程度(ご自身で行う場合)。
- 法務局での審査期間:申請してから1週間〜2週間程度。
合計すると、相続開始から登記完了まで、一般的には数ヶ月から半年程度が目安となります。複雑なケースや相続人間でトラブルがある場合は、1年以上かかることも珍しくありません。
かかる費用の目安
- 登録免許税
不動産の固定資産評価額の0.4%が原則です。
例:評価額が2,000万円の不動産の場合、2,000万円 × 0.004 = 8万円 となります。
建物と土地が別々に評価されている場合は、それぞれの評価額を合算した金額に対して計算します。
特定の条件を満たす土地や建物については、税率が軽減される特例(住宅用家屋の所有権移転登記の軽減税率など)がある場合もあります。 - 必要書類の取得費用
戸籍謄本:1通 450円程度
除籍謄本・改製原戸籍謄本:1通 750円程度
住民票:1通 300円程度
印鑑証明書:1通 300円程度
固定資産評価証明書:1通 300円程度
郵送費:数百円〜数千円
これらを合計すると、数千円〜1万円程度かかるのが一般的です。 - 専門家への報酬(依頼した場合)
司法書士報酬
相続登記の一般的な報酬は、5万円〜15万円程度が目安です(不動産の数や評価額、複雑さによって変動します)。
遺産分割協議書の作成なども含めると、さらに費用がかかる場合があります。
弁護士報酬
遺産分割協議の代理や交渉を依頼する場合、着手金と成功報酬が発生します。事案の複雑さや争いの有無によって大きく異なり、数十万円〜数百万円かかることもあります。
税理士報酬
相続税申告を依頼する場合、相続財産の総額によって変動しますが、数十万円〜数百万円が目安です。

ご自身で手続きを進める場合は、上記の「登録免許税」と「必要書類の取得費用」のみで専門家報酬は発生しないため、費用を抑えることができますが、手間と時間は非常にかかります。
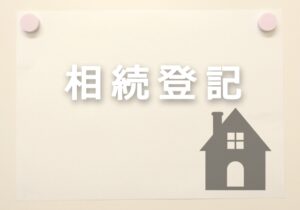
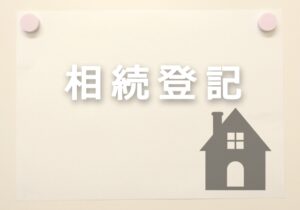
無料でできる不動産相続手続きとは?


不動産の相続手続きを費用をかけずに進めるには、ご自身で申請を行う「セルフ登記」が基本となります。また、公的機関が提供する無料相談窓口を上手に活用することも重要です。
自分で申請する方法(セルフ登記)
相続登記(不動産の名義変更)は、司法書士などの専門家に依頼せずに、ご自身で法務局に申請することができます。これを「セルフ登記」と呼びます。
セルフ登記のメリット
- 費用を抑えられる:司法書士への報酬が不要になるため、登録免許税や書類取得費用などの実費のみで手続きを進めることができます。
セルフ登記のデメリット
- 手間と時間がかかる:必要書類の収集、申請書の作成、法務局での手続きなど、全てご自身で行うため、多くの時間と労力が必要です。
- 専門知識が必要:不動産登記に関する専門知識がないと、書類の不備や記載ミスが生じやすく、何度も法務局に足を運ぶことになる可能性があります。
- 複雑なケースへの対応:相続人が多数いる、行方不明の相続人がいる、遺産分割で揉めているなど、複雑なケースではセルフ登記が非常に困難になる場合があります。
セルフ登記の主な流れ
- 必要書類の収集
- 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本を含む)
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
- 相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書
- 不動産の固定資産評価証明書
- 遺産分割協議書(遺言書がない場合)または遺言書
- その他、ケースに応じた書類
- 登記申請書の作成
- 法務局のウェブサイトからひな形をダウンロードし、必要事項を正確に記入します。
- 不動産の表示(所在地、地番、家屋番号など)や、相続関係、申請内容などを記載します。
- 法務局への申請
- 作成した申請書と必要書類を、不動産の所在地を管轄する法務局に提出します。
- 郵送での申請も可能ですが、不備があった場合の対応を考えると、窓口での提出が確実です。
- 補正対応・完了
- 法務局の担当者から書類の不備(補正)を指摘された場合は、指示に従って修正・追加提出を行います。
- 問題がなければ登記が完了し、新しい名義の登記識別情報通知(権利証)が発行されます。
法務局の無料相談を活用する
法務局では、相続登記に関する無料の相談窓口が設けられています。セルフ登記を検討している方にとって、非常に有効な支援です。
- 「登記手続案内」
法務局が提供している無料の相談サービスです。
登記申請書の書き方や、添付書類の確認、手続きの流れなどについて、登記官や相談員がアドバイスしてくれます。 - ポイント:個別の具体的なケースについて、法的な判断や代理行為は行いません。あくまで申請書の作成や手続きに関する情報提供が中心です。
- 利用方法:事前予約が必要な場合が多いので、管轄の法務局のウェブサイトを確認するか、電話で問い合わせて予約を取りましょう。相談時間は1回あたり20分程度と限られていることが多いです。
- 形式:窓口での対面相談のほか、電話やウェブ会議サービスでの相談に対応している法務局もあります。
市区町村・法テラスなどの無料支援窓口紹介
法務局以外にも、無料で相続に関する相談ができる公的機関や団体があります。
- 市区町村役場
- 多くの市区町村役場では、住民向けに弁護士、司法書士、税理士などによる無料法律相談会や相続相談会を定期的に開催しています。
- 相続手続き全般に関する一般的な疑問や、どの専門家に相談すべきかといった初期段階の相談に適しています。
- 法テラス(日本司法支援センター)
- 経済的に余裕がない方(一定の資力基準を満たす方)を対象に、弁護士や司法書士による無料法律相談を提供しています。
- 1つの問題につき3回まで(1回30分程度)無料で相談できます。
- 相続人間でトラブルが発生している場合や、専門家への依頼費用が心配な場合に活用を検討できます。
- 税務署
- 相続税に関する一般的な相談を無料で受け付けています。
- 相続税の計算方法や、申告書の書き方、納税方法などについて相談できます。
- 相続税の節税対策や、個別の具体的な税務相談はできません。
- 弁護士会・司法書士会・行政書士会
- 各士業団体が、初回無料相談や無料相談会を実施していることがあります。
- ウェブサイトで情報を確認するか、直接問い合わせてみましょう。
不動産の相続手続きが無料!?各専門家が勢ぞろいの新サービス!
\不動産相続のご相談は、クルーズカンパニーにお任せください/
専門家の得意分野と活用方法
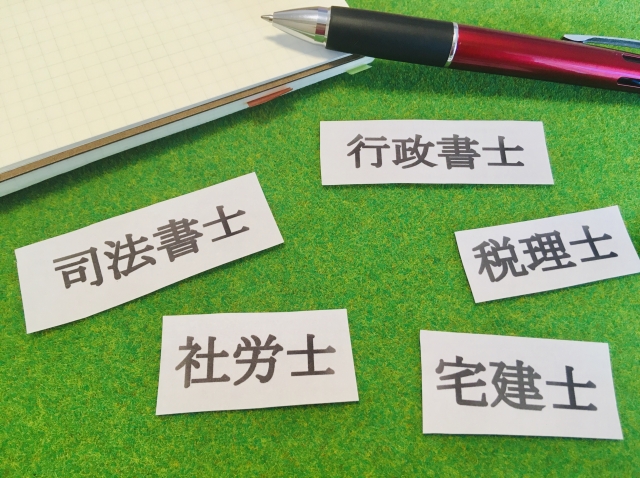
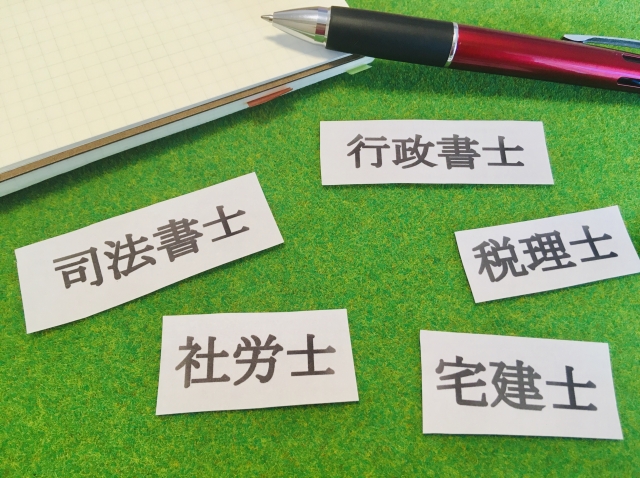
不動産の相続は、複雑な手続きや専門的な知識が求められることが多く、トラブルを避けるためにも専門家の活用を検討することが重要です。
各専門家の役割と得意分野
司法書士
不動産の相続登記(名義変更)、遺産分割協議書の作成支援、遺言書作成支援、相続放棄、成年後見など、不動産登記や裁判所提出書類作成に強みがあります。
活用方法
- 相続登記の方法が知りたい場合:自分で登記を進めたいが手順や必要書類に不安がある場合、具体的に相談できます。
- 遺産分割協議書の作成で悩んでいる場合:適切な書式や記載内容についてアドバイスがもらえます。
- 相続人が多くて、戸籍収集が大変な場合:戸籍の取り寄せ方や、法定相続情報証明制度の利用について相談できます。
- 費用相場を知りたい場合:実際に依頼した場合の費用感を聞くことができます。
弁護士
相続人間の紛争解決(遺産分割協議の調停・審判、遺留分侵害額請求など)、遺言書の有効性に関する問題、相続放棄に関する複雑なケースなど、法律紛争全般に強みがあります。
活用方法
- 相続人同士で遺産分割の意見がまとまらない場合:どのような解決策があるか、調停や審判に移行した場合の流れなどを相談できます。
- 遺留分を侵害されていると感じる場合:請求が可能か、どのような手続きが必要かなどを相談できます。
- 特定の相続人が財産を隠している疑いがある場合:調査方法や法的措置について相談できます。
- 相続放棄を検討しているが、複雑な事情がある場合:専門的なアドバイスがもらえます。
税理士
相続税の計算・申告、節税対策、不動産の評価、贈与税相談に強みがあります。
活用方法
- 相続税がかかるのかどうか知りたい:相続税がどのくらいかかるのかを聞くことができます。
- 相続税を少しでも安くしたい:相続税を安くするアドバイスがもらえます。
- 将来の相続(二次相続)を見据えた対策:一般的な方向性を知りたい場合に相談できます。
行政書士
遺産分割協議書の作成、遺言書作成支援、相続関係図の作成、自動車の名義変更など、行政機関への提出書類作成や手続きの代理に強みがあります。
活用方法
- 遺産分割協議書を自分で作成したいが、書き方がわからない場合:法的な要件を満たした協議書の作成について相談できます。
- 相続関係が複雑で、相続人調査に不安がある場合:相続関係図の作成についてアドバイスがもらえます。
- 遺言書を作成したいが、何から手をつけて良いか分からない場合:遺言の種類や記載内容について相談できます。
専門家に相談する前に準備しておくといい事
- 事前に相談内容を整理しておく:何を一番聞きたいのか、具体的な状況(誰が亡くなったか、相続人は何人か、主な財産は何かなど)を簡潔にまとめておくとスムーズです。
- 関連資料を持参する:故人の戸籍謄本、不動産の固定資産税納税通知書、遺言書など、もし手元にあれば持参すると、より具体的なアドバイスがもらえます。
- 質問リストを作成する:限られた時間なので、聞きたいことをリストアップしておきましょう。
- 目的を明確にする:ただ相談したいのか、それとも具体的な依頼を検討しているのかを伝えると、専門家も適切なアドバイスがしやすくなります。



専門家との相談時には、事前に相談内容と書類を準備しておくことが、最大限の活用につながります!
まとめ
不動産の相続手続きを無料で進めるには、ご自身で手続きを行う「セルフ登記」が基本です。しかし、専門知識や多くの手間がかかるため、公的機関や専門家が提供する無料相談窓口を賢く活用することが重要です。
クルーズカンパニーでは、不動産相続手続きの相談だけではなく、専門家の手続きの費用まで無料で行うサービスをはじめております!
不動産の相続手付きの際には、是非お気軽にご連絡ください!
不動産の相続手続きが無料!?各専門家が勢ぞろいの新サービス!
\不動産相続のご相談は、クルーズカンパニーにお任せください/


| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 定休日 | 無休(年末年始、夏季、GWを除く) |
| 住所 | 東京都千代田区飯田橋4-8-13 山商ビル2F |
| 電話番号 | 03-3556-3101 |











