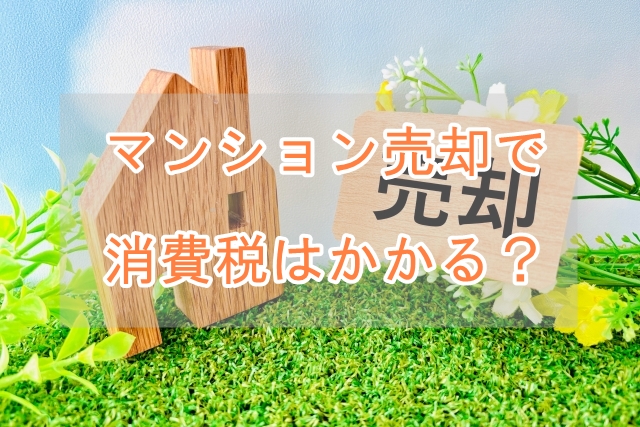マンションを売却する際、意外と見落とされがちなのが「消費税」です。
消費税は、国内で事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等に課税される税金です。
マンション売却は高額な取引でありながら、消費税がかかるケースとかからないケースが明確に分かれています。
この記事では、マンション売却時における消費税の基本的な取り扱いを解説し、特に「消費税がかからない」ケース、消費税額の計算方法、仲介手数料などの諸費用の扱い、そしてその他の税金や節税のポイントについて、具体的な内容をまとめています。
正確な知識を持つことで、予期せぬ税負担を回避し、売却による手取り額を最大化するための計画を立てることが可能になりますので、是非参考にしてみてください。
マンション売却後の節税対策も無料でサポート!
\マンション売却は、クルーズカンパニーにお任せください/
マンション売却における「消費税」の基本

マンション売却における消費税の基本的な取り扱いは、誰が何を売るのかによって大きく異なります。
消費税が課される取引と課されない取引の違い
消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や役務の提供に対して課税されます。
| 区分 | 定義 | 消費税の扱い |
| 課税取引 | 課税の要件(国内での事業者の事業活動、対価性など)を満たす取引。 | 消費税が課される(納税義務は課税事業者に限る)。 |
| 不課税取引 | 課税の要件を満たさない取引(例:個人の生活用資産の売却、給与など)。 | 消費税がかからない。 |
| 非課税取引 | 課税の要件は満たすが、政策的配慮から消費税法で非課税と定められている取引(例:土地の譲渡、住宅の家賃など)。 | 消費税がかからない。 |
【マンション売却における重要なポイント】
- 事業者が行う売却:原則として課税取引となります(建物部分のみ)。
- 個人(非事業者)が行う売却:事業ではないため、不課税取引となります(自宅など生活用資産の売却)。
不動産売却における「土地」と「建物」の扱いの違い
不動産を売却する場合、土地と建物で消費税の扱いが明確に分けられます。
| 対象 | 消費税の扱い | 理由 |
| 土地(借地権含む) | 非課税 | 土地は消費されるものではなく、資本の移転とみなされるため。 |
| 建物 | 原則として課税 | 人の活動によって作られた付加価値(資産)であり、消費税の課税対象となるため。 |
マンション売却では、土地の敷地利用権と建物を一括で売却しますが、売買契約書などで土地部分と建物部分の価格を区分し、建物部分にのみ消費税が課される(または不課税・非課税になる)ことになります。
居住用・投資用・事業用マンションの税区分
売主の属性(個人か法人か、課税事業者か免税事業者か)と、マンションの用途によって、建物部分の消費税の扱いは以下のように異なります。
| 売主の属性 | マンションの用途 | 建物部分の消費税の扱い |
| 個人(サラリーマンなど) | 居住用(マイホーム、セカンドハウス) | 不課税(事業ではない個人の生活用資産の譲渡のため)。 |
| 個人事業主 | 居住用(自宅) | 不課税(事業用資産ではないため)。 |
| 個人事業主 | 投資用(賃貸マンション)※1 | 課税(事業用資産の譲渡のため)。ただし、免税事業者の場合は納税義務なし。 |
| 法人 | 事業用(事務所・店舗、賃貸マンションなど) | 課税(事業者が行う資産の譲渡のため)。ただし、免税事業者の場合は納税義務なし。 |
| 法人 | 居住用(社宅など) | 法人が所有する建物はすべて事業用資産となるため課税(免税事業者は納税義務なし)。 |
※1:個人が売主で、そのマンションを居住用として賃貸していた場合、建物部分の売却は課税対象となりますが、前々年の課税売上高が1,000万円以下などの条件を満たせば免税事業者となり、買主から消費税を預かり納税する義務は免除されます。
課税事業者:基準期間(原則として前々年)の課税売上高が1,000万円を超えるなど、消費税の納税義務がある事業者。
免税事業者:基準期間の課税売上高が1,000万円以下などの理由で、消費税の納税義務が免除されている事業者。
消費税が「かかる」ケース

マンション売却で消費税が「かかる」ケースは、主に売主が事業者であることと、売却物件が事業用資産であることの2点が関わってきます。
土地は常に非課税ですが、建物部分について以下のケースで消費税が課税されます(ただし、売主が免税事業者である場合は納税義務はありません)。
不動産会社や法人が販売する場合(課税事業者)
不動産会社や法人は「事業者」にあたるため、その事業活動として行うマンションの売却は、原則として消費税の課税対象となります。
- 新築マンションの売却:売主がデベロッパーや販売会社(法人)であるため、建物価格に消費税が課税されます。
- 法人所有の中古マンション売却:会社が事業用として保有していた物件(事務所、社宅、投資用物件など)を売却する場合、建物価格に消費税が課税されます。
- 不動産買取再販物件の売却:不動産会社が個人から中古物件を買い取り、リフォーム・リノベーションを施して再販売する場合(売主が不動産会社になる)は、建物価格に消費税が課税されます。
事業用マンション(賃貸・オフィス・テナント等)の売却
売主が個人・法人を問わず、事業として使用していた建物を売却する場合は、原則として消費税の課税対象となります。
投資用(賃貸)マンションの売却
- 売主が法人であれば、原則として課税されます。
- 売主が個人であっても、賃貸経営は「事業」とみなされるため、建物部分の売却は課税取引に該当します。ただし、後述の「個人事業主の注意点」により、免税事業者であれば納税は不要です。
オフィス・店舗(テナント)用マンションの売却:
- 売主が法人または個人事業主であれば、事業用資産の譲渡として建物部分に消費税が課税されます。
個人事業主が売却する場合の注意点
個人事業主の売却は、物件の用途と納税義務の有無によって扱いが異なります。
| 売却物件の用途 | 消費税の課税判断 | 納税義務の有無の注意点 |
| 居住用(自宅・マイホーム) | 不課税(事業用資産ではない) | 納税義務の有無にかかわらず、建物・土地ともに消費税はかからない。 |
| 事業用(賃貸、事務所など) | 課税(事業用資産の譲渡) | 売主が「課税事業者」か「免税事業者」かで納税義務が変わる。 |
消費税が「かからない」ケース

マンション売却において、売買価格に対する消費税が「かからない」ケースは、主に売主が個人であり、売却する資産が生活用である場合と、売却対象が土地である場合です。
個人が自宅マンションを売却する場合(不課税)
消費税は「国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡」に対して課税されます。そのため、事業を行っていない一般的な個人が行う自宅の売却は、この課税要件を満たさないため、消費税はかかりません。
| 対象 | 消費税の扱い | 理由 |
| 土地部分 | 非課税 | 土地は消費財ではないため(売主が誰であっても非課税)。 |
| 建物部分 | 不課税 | 個人(非事業者)による生活用資産(自宅、セカンドハウスなど)の譲渡は、事業ではないため、課税対象外(不課税)となります。 |

売主が個人事業主であっても、事業用ではない自宅やセカンドハウスの売却であれば、同様に建物部分も消費税はかかりません。
居住用財産の譲渡所得における非課税条件(消費税との区別)
「居住用財産の譲渡における非課税条件」という言葉は、消費税ではなく、売却益(譲渡所得)にかかる所得税・住民税の特例を指します。消費税と譲渡所得税は全く別の税金なので注意が必要です。
| 税金の種類 | 目的・対象 | 非課税(控除)の特例 |
| 消費税 | モノやサービスの消費に課税される税金。 | 個人のマイホーム売却は、そもそも不課税で消費税はかかりません。 |
| 譲渡所得税・住民税 | 不動産売却で得た利益(譲渡所得)に課税される税金。 | 「3,000万円の特別控除」など。 |
| 居住用財産の譲渡所得に関する主な特例 | 概要 |
| 3,000万円の特別控除 | 自宅を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、最高3,000万円まで控除できる特例。譲渡所得税・住民税を軽減またはゼロにできます。 |
| 軽減税率の特例 | 10年超所有した自宅を売却する場合、譲渡所得6,000万円までの部分について低い税率(軽減税率)を適用できる特例。 |



自宅売却は消費税はかかりませんが、利益が出れば譲渡所得税・住民税がかかるため、上記の特例が重要になります。
相続や贈与による売却時の扱い
相続や贈与によって取得したマンションを売却する場合も、売主が個人であることに変わりはないため、基本的な消費税の原則が適用されます。
| 売却の種類 | 消費税の扱い | 譲渡所得税の注意点 |
| 相続したマンションの売却 | 不課税(売主が個人のため) | 相続税の申告期限から3年以内に売却した場合、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」が適用できることがあります。 |
| 贈与したマンションの売却 | 不課税(売主が個人のため) | 贈与の場合は譲渡所得税の特例は適用されませんが、贈与税や不動産取得税などの別の税金が発生します。 |


消費税額の計算方法


マンション売却で消費税額を計算する際は、売主が課税事業者である場合、売却価格全体ではなく、建物部分の価格のみを対象として税率をかけます。土地の売却は消費税の対象外です。
消費税額の計算方法の基本
消費税が課税されるのは、売主が課税事業者(法人や一部の個人事業主)であり、かつ事業用資産(建物)を売却する場合です。
課税対象となる建物部分の価格に対する税率(10%)
消費税額の計算は、以下の式に基づきます。
消費税額=建物売却価格(税抜)×消費税率(10%)
- 建物価格の算定:マンションの売買では土地と建物を一括で取引するため、売買契約書等で土地と建物の価格を明確に区分する必要があります。区分されていない場合は、固定資産税評価額や相続税評価額などの比率に基づき、按分して計算します。
土地は非課税になる理由
土地の売却が非課税とされる理由は、消費税が持つ「消費」に負担を求める税としての性格にあります。
- 非消費性:土地は、建物や商品のように使用や時間の経過によって価値が減耗し、消費される財とはみなされません。
- 資本の移転:土地の譲渡は、単なる資本の移転として捉えられます。
- 消費税法の規定:したがって、消費税法において、土地の譲渡および貸付けは課税対象としてなじまないものとして非課税取引に定められています。



売主が事業者であるか個人であるか、また売却物件が居住用か事業用かにかかわらず、土地部分には消費税は一切かかりません。
シミュレーション例:3,000万円のマンション売却
売主が課税事業者であり、事業用マンション(賃貸用など)を総額3,000万円で売却する場合をシミュレーションします。
【前提条件】
| 項目 | 金額(税込総額) | 備考 |
| 売却総額 | 3,000万円 | 建物価格と土地価格を含む総額 |
| 建物価格(税抜) | 1,500万円 | 建物部分の価格(シミュレーションのため設定) |
| 土地価格 | 1,363.64万円 | 土地部分は非課税 |
| 消費税率 | 10% | (国税7.8%+地方消費税2.2%) |
【建物価格と消費税額の計算】
売却総額3,000万円が税込価格であるとすると、そこに含まれる消費税額は、以下の計算で求められます。
- 建物価格の税込金額を計算:建物税込価格=建物税抜価格×(1+0.10)
- 売却総額から消費税額を算出:このシミュレーションでは、建物税抜価格が1,500万円と設定されているため、消費税額=建物税抜価格×10%消費税額=1,500万円×0.10=150万円
【結果】
| 項目 | 金額 | 備考 |
| 建物売却価格(税抜) | 1,500万円 | 課税対象 |
| 土地売却価格 | 1,363.64万円 | 非課税対象 |
| 消費税額 | 150万円 | 建物部分に課税される額 |
| 売却総額(税込) | 3,013.64万円 | (1,500万円 + 150万円 + 1,363.64万円) |
- 上記は売主が消費税の課税事業者であり、事業用資産を売却した場合の計算例です。
- 個人が自宅を売却する場合は、建物部分も不課税であるため、売却総額に対する消費税は0円です。
- 実際に買主から預かった消費税額は、その取引で支払った消費税額(仲介手数料など)を差し引いたうえで、税務署に納税します(仕入税額控除)。


消費税を含む「諸費用・仲介手数料」の注意点
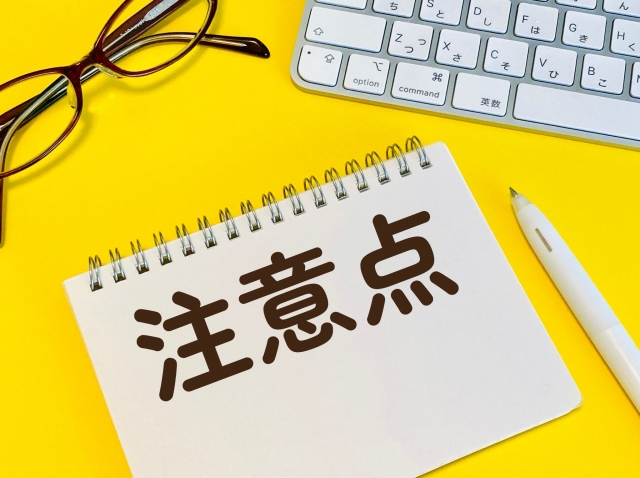
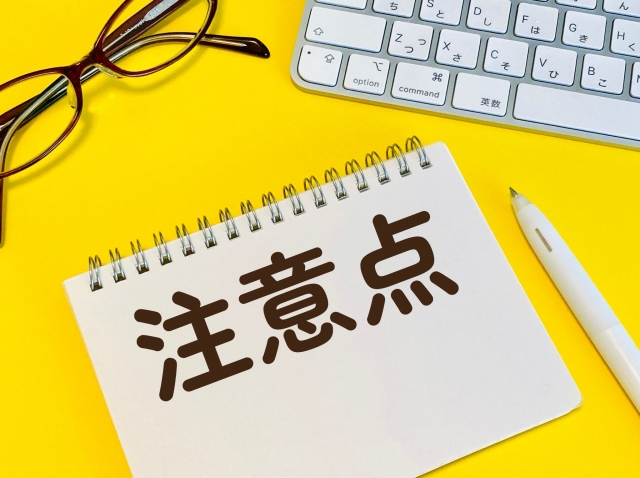
マンション売却における諸費用や仲介手数料は、本体価格とは別に消費税がかかることが多いため、注意が必要です。特に売主が個人か事業者かによって、その取り扱いが大きく異なります。
仲介手数料・司法書士報酬にかかる消費税
仲介手数料
不動産会社に支払う仲介手数料は、不動産会社が提供する「サービス(役務の提供)」に対する対価です。
- 消費税はかかる:売主が個人であっても法人であっても、売却物件が自宅(非課税)であっても事業用(課税)であっても、仲介手数料には例外なく消費税(10%)が課税されます。
- 注意点:仲介手数料の上限額(速算式:売買価格の3%+6万円)は税抜で定められているため、最終的な支払額はこれに消費税を加えた金額となります。
司法書士報酬
売却に伴う登記手続き(抵当権抹消登記など)を司法書士に依頼する際の報酬についても、「サービス(役務の提供)」に対する対価であるため、原則として消費税(10%)が課税されます。
- 非課税な部分: 司法書士に支払う費用に含まれる登録免許税(税金)や、公的な証明書の発行手数料などは、税金や行政手数料であるため消費税は非課税です。
買取再販や建物解体費にかかる税金の取り扱い
買取再販(売主が業者)
不動産会社が中古物件を買い取り、リノベーションなどをして再販(売主として販売)する場合、その取引は不動産会社の「事業」として行われます。
- 建物価格: 建物部分には消費税が課税されます。買主はこの消費税を負担しますが、不動産会社は仕入れ(リフォーム費用や元の建物購入費)で支払った消費税を差し引いて納税します(仕入税額控除)。
- 注意点: 買主がこの物件を購入した場合、売主が個人の中古物件を購入する場合(建物部分が不課税)よりも、物件価格が高くなります。
建物解体費
土地を売却するために、古い建物を解体して更地にする場合の費用には、二つの側面で税金の取り扱いがあります。
- 解体工事費にかかる消費税
- 解体業者に支払う解体工事費は「役務の提供」に対する対価であり、消費税(10%)が課税されます。
- 譲渡所得税の計算
- 建物の解体費用は、土地の売却を成立させるために直接かかった費用として、「譲渡費用」に含めることができます。譲渡費用は売却益(譲渡所得)を計算する際に控除できるため、所得税・住民税を節税する効果があります。
- 譲渡所得=売却価格−(取得費+譲渡費用)
消費税の課税事業者・免税事業者の違い
売主が法人または個人事業主(不動産投資家など)である場合、その物件の売却に消費税の納税義務があるか否かは、「課税事業者」か「免税事業者」かによって決まります。
| 項目 | 課税事業者 | 免税事業者 |
| 定義(原則) | 基準期間(個人:前々年、法人:前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を超える事業者。 | 基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者。 |
| 消費税の納税義務 | 有り。事業用建物の売却で預かった消費税を納税する必要がある。 | 無し。消費税を預かっても納税は免除される。 |
| 仕入税額控除 | 適用できる。仲介手数料などで支払った消費税を、売却で預かった消費税から差し引ける。 | 適用できない。支払った消費税を差し引くことはできない。 |
不動産売却における注意点
- 個人事業主が事業用不動産を売却する場合:売却によって建物価格が多額の課税売上高となるため、その取引があった年の翌々年に課税事業者となる可能性が高くなります。これにより、翌々年以降の賃貸収入などの課税売上にも消費税の納税義務が生じることになります。
- 自宅の売却:個人が自宅(生活用資産)を売却する場合は、事業に該当しないため、課税事業者であっても建物部分の売却代金には消費税はかかりません。
マンション売却時に関係するその他の税金


マンション売却時に関係する税金は、消費税だけでなく、売却益にかかる譲渡所得税(所得税・住民税)や、契約書や登記にかかる印紙税・登録免許税など、多岐にわたります。
所得税・住民税(譲渡所得税)との違い
マンション売却で最も重要となるのが、売却益に対してかかる譲渡所得税です。
譲渡所得税の仕組み
譲渡所得税は、売却によって得た利益(譲渡所得)に対して課税される税金で、所得税と住民税の合計額です。これは、売却価格全体にかかる消費税とは根本的に異なります。
| 項目 | 譲渡所得税(所得税・住民税) | 消費税 |
| 課税対象 | 売却益(譲渡所得) ※1 | 建物部分の売却価格 ※2 |
| 売主 | 個人(全員) | 課税事業者(法人や一部の個人事業主) |
| 計算式 | (売却価格−取得費−譲渡費用)×税率 | 建物価格×10% |
※1 自宅売却の場合、3,000万円特別控除などの特例で大幅に軽減されることが多いです。
※2 仲介手数料などの諸費用には、売主・買主を問わず消費税がかかります。
譲渡所得税の税率
譲渡所得税の税率は、マンションを所有していた期間(売却した年の1月1日時点)によって大きく異なります。
| 所有期間 | 区分 | 所得税(復興特別所得税含む) | 住民税 | 合計税率 |
| 5年以下 | 短期譲渡 | 30.63% | 9% | 39.63% |
| 5年超 | 長期譲渡 | 15.315% | 5% | 20.315% |



長期譲渡の方が税率が約半分になるため、売却のタイミングは非常に重要です。
印紙税・登録免許税の扱い
不動産売却時に発生するその他の税金は、その性質から消費税はかかりません。
📄 印紙税
印紙税は、経済取引に伴い作成される特定の文書(契約書や領収書など)に課税される国税です。
- 課税文書:不動産売買における「不動産売買契約書」が代表的な課税文書です。
- 税額:契約書に記載された売買金額に応じて税額が決まっています(収入印紙を貼付)。
- 消費税:印紙税そのものは税金であるため、消費税は非課税です。
📜 登録免許税
登録免許税は、不動産の登記を行う際に課税される国税です。
- 課税対象
売主:住宅ローンを完済した際に不動産についている「抵当権を抹消する登記」を行う際に発生します。
買主:新しい所有者として「所有権移転登記」を行う際に発生します(通常は買主負担)。 - 税額:原則として不動産の数1個につき1,000円です。土地と建物で2個となるため、抵当権抹消登記では2,000円が一般的です。
- 消費税:登録免許税そのものは税金であるため、消費税は非課税です。
税務署への確定申告のポイント
マンションを売却し、売却益(譲渡所得)が発生した場合は、原則として確定申告が必要です。特に特例を適用する場合は必須です。
| 申告の必要性 | 詳細 |
| 必須 | 売却益(譲渡所得)が発生した場合。特に、長期譲渡所得の軽減税率や居住用財産の特例(3,000万円特別控除など)を適用する場合。 |
| 推奨 | 売却損(譲渡損失)が発生した場合。特定の要件を満たせば、給与所得など他の所得と損益通算し、所得税・住民税を軽減できる場合があります。 |
| 原則不要 | 特例の適用により譲渡所得が0円以下になった場合。ただし、上記の売却損の特例を適用する場合は申告が必要です。 |
申告時の重要ポイント
- 譲渡費用・取得費の証明
確定申告で譲渡所得を正確に計算するためには、取得費(購入時の価格や仲介手数料など)と譲渡費用(売却時の仲介手数料、印紙税など)を証明する領収書や契約書が不可欠です。紛失すると計算が不利になる場合があります。 - 特例の適用
マイホームの売却の場合、「3,000万円特別控除」や「買換え特例」など、適用要件が厳格に定められた複数の特例があります。これらの特例は基本的に併用できないため、最も有利なものを選択し、その要件を満たしていることを確認する必要があります。 - 申告時期
不動産を売却した翌年の2月16日から3月15日までに、所轄の税務署へ申告します。納税もこの期間内に行う必要があります。


節税・還付を受けるためのポイント


マンション売却において税負担を最小限に抑えるためには、譲渡所得税の特例の活用と、一部の事業者向けの消費税還付の仕組みを理解することが重要です。
居住用財産の3,000万円特別控除との関係
「3,000万円特別控除」は、譲渡所得税(所得税・住民税)の節税の柱となる特例であり、消費税の還付とは直接的な関係はありませんが、売却全体の税負担を大きく軽減します。
特徴と節税効果
対象
個人が所有するマイホーム(居住用財産)を売却し、利益(譲渡所得)が出た場合。
効果
譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。これにより、ほとんどのマイホーム売却では譲渡所得がゼロとなり、所得税・住民税の負担がなくなります。
消費税との関係
- 売却代金:個人が自宅を売却する場合、建物部分も消費税はかかりません(不課税)。この特例は、売却益(譲渡所得)にかかる所得税・住民税を減らすためのものであり、消費税を減らす特例ではありません。
- 確定申告:この特例を適用して税金をゼロにする場合でも、売却した翌年に確定申告を行うことが必須です。申告しなければ特例は適用されません。
消費税還付を受けられるケース(投資用マンション等)
一般の個人による自宅売却では消費税還付は関係ありませんが、投資用不動産を所有する課税事業者(法人や一部の個人事業主)は、不動産購入や大規模修繕時に消費税還付を受けられる可能性があります。
還付の基本的な仕組み
消費税は「(受け取った消費税)-(支払った消費税)」を納税する仕組みです。新しい事業用建物を購入するなど、多額の支払った消費税が受け取った消費税を上回った場合に、その差額が還付されます。
還付額=(支払った消費税額)−(受け取った消費税額)
投資用不動産と還付の規制
| 項目 | 扱いの原則 | 重要な注意点 |
| 居住用賃貸物件 | 原則、還付不可 | 令和2年度(2020年度)の税制改正により、アパートやマンションなどの居住用賃貸物件の取得に係る消費税は、仕入税額控除の対象外となり、原則として還付は受けられなくなりました。 |
| 事業用賃貸物件 | 還付可能 | 店舗や事務所、テナントビルなど、家賃が課税売上となる事業用物件の取得については、現在も還付を受けることが可能です。 |
| 還付を受けるための条件 | 課税事業者であること。また、課税売上割合が高いことなどの要件があります。 |



消費税還付の制度は非常に複雑であり、還付を受けた後に建物の用途変更や売却を行うと、還付された消費税の一部を再調整・納税しなければならない場合(3年間など)があるため、専門的な知識が必要です。
不動産会社・税理士に相談すべきタイミング
節税を成功させるためには、売却活動を始める前の早期段階で専門家に相談することが最も重要です。
不動産会社への相談タイミング
| 相談内容 | ベストな時期 | 理由 |
| 売却価格設定 | 売却活動を始める前 | 税金(譲渡所得税)の負担額を考慮した上で、手取り額を最大化するための適正な売却価格を検討するため。 |
| 所有期間の調整 | 売却希望時期の1年以上前 | 所有期間が「5年超」になるまで売却を遅らせることで、税率を約半分(短期→長期)にでき、手取り額が大きく変わるため。 |
税理士への相談タイミング
| 相談内容 | ベストな時期 | 理由 |
| 譲渡所得税の節税 | 売却を検討し始めた時点 | 3,000万円特別控除や買換え特例など、どの特例を適用すべきか、特例を適用するための売却期限はいつかなど、売却計画全体を最適化するため。 |
| 消費税の還付 | 投資用物件の取得・建設前 | 還付を受けるためには、建物を取得する前に課税事業者になるための届出(課税事業者選択届出書など)を期限内に提出する必要があるため。 |
| 確定申告 | 売却した年の年末まで | 確定申告の準備(必要書類の収集、譲渡所得の計算など)をスムーズに行い、期限内の申告を確実にするため。 |


まとめ
マンション売却における消費税は、「誰が売るか」「どのような用途の物件か」 によって大きく変わります。
個人が自宅として使っていたマンションを売却する場合は非課税ですが、法人や不動産事業者が販売する場合、または事業用・投資用マンションの売却は課税対象となります。
特に注意すべきは、建物部分のみが課税対象で土地は非課税である点、そして仲介手数料や登記費用などの諸経費には消費税がかかるということです。
また、居住用財産の3,000万円特別控除や譲渡所得税との関係も理解しておくことで、節税効果を最大化できます。
売却の際は、税理士や不動産会社と連携し、課税・非課税の判断を正確に行うことが重要です。
クルーズカンパニーではマンション売却後のサポートも万全の体制を用意しておりますので、お気軽にご相談ください!


マンション売却後の節税対策も無料でサポート!
\マンション売却は、クルーズカンパニーにお任せください/