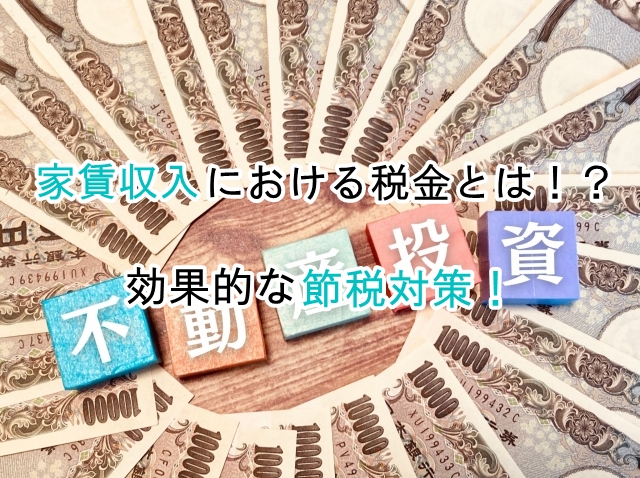マンションやアパート、一戸建てなどを所有し、賃貸として経営して家賃収入を得ているオーナーにとって「税金対策」は重要なことです。家賃収入は所得として課税対象となるため、正しい知識を持たずに申告してしまうと「余分な税金を払ってしまう」ケースや「思わぬ税務調査」に発展するケースも少なくありません。
この記事では、家賃収入における税金の種類から節税の具体的な方法、法人化や相続対策までを体系的に解説します。これから賃貸経営を始める方だけでなく、すでに不動産オーナーとして活動している方にも役立つ内容になっておりますので、収入に対するオフェンス面だけれはなく、支出面に対するディフェンス面も一緒に考えてみましょう。
賃貸管理に強い不動産会社へ今すぐ無料でご相談!
\「賃貸経営の専門家」節税対策もしっかりサポート/
家賃収入にかかる税金の種類

家賃収入は不動産所得として所得税と住民税の課税対象になります。また、ご所有不動産にも固定資産税・都市計画税がかかります。以下で税金の種類を解説します。
所得税(不動産所得)
家賃収入は「不動産所得」として所得税の対象になります。給与所得や事業所得と合算され、累進課税(最大45%)の対象となる点に注意が必要です。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
| 1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
※平成25年から令和19年までの各年分の確定申告においては、所得税と復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1パーセント)を併せて申告・納付することとなります。
住民税
前年の所得に応じて、翌年に課されるのが住民税。都道府県民税・市町村民税を合わせて、通常10%前後が課税されます。
固定資産税・都市計画税
不動産オーナーにとっては毎年かかる「持ち続けるコスト」。課税標準額に税率をかけて算出され、建物や土地の評価額によって金額が変わります。
消費税が発生するケース
住宅用の家賃は非課税ですが、駐車場や事務所などの賃貸料は課税対象です。賃貸用途によって課税の有無が異なるため要注意です。
※貸主が免税事業者である場合、インボイスの発行が出来ず、消費税額の仕入税額控除を受けることができません。
家賃収入にかかる税金の計算方法

家賃収入(不動産所得)にかかる税金の計算方法を解説します。
不動産所得の計算式
不動産所得 = 総収入金額 - 必要経費
総収入金額:賃貸経営で得られる以下の収入は、すべて課税対象の「総収入金額」に含まれます。
- 毎月の家賃
- 共益費や管理費(入居者から受け取った分)
- 礼金・更新料・敷引金(敷金のうち返還しない部分)
- 駐車場代
- 看板設置料など不動産利用に伴う収入
※敷金や保証金など返還する前提のものは収入に含まれません。
必要経費:賃貸経営でかかった支出は「必要経費」として控除可能です。
- 固定資産税・都市計画税
- 減価償却費(建物・設備の購入費用を耐用年数で分割)
- ローン利息(元本返済分は経費にならないので注意)
- 修繕費(原状回復や維持管理のための修繕)
- 管理委託費(賃貸管理会社に払う手数料)
- 火災保険・地震保険料
- 水道光熱費(オーナー負担分)
- 交通費や通信費(不動産管理に関連する部分)
※必要経費は「賃貸経営に直接関係する支出であること」であり、プライベートな支出を混ぜると税務調査で指摘されるリスクがあります。
青色申告と白色申告
青色申告なら最大65万円の特別控除があり、家族に給与を払って経費にできる「専従者給与制度」も利用可能です。

家賃収入の節税対策

家賃収入がある場合、原則として毎年確定申告が必要です。「家賃収入に対する節税対策」を詳しく解説します。
青色申告の活用
不動産所得が事業規模であると認められる場合、青色申告は税負担を大きく軽減する強力な手段です。
事業規模の目安
- 独立した建物(戸建て)の場合:おおむね5棟以上
- アパートやマンションの場合:おおむね10室以上
- 戸建て1棟はアパート2室分に、駐車場5台分はアパート1室分に換算
青色申告の主なメリット
青色事業専従者給与
生計を共にする親族に支払う給与を、要件を満たせば全額経費にすることができます。これにより、所得の分散を図り、世帯全体の税負担を軽減できます。
例)事業主の所得1,000万円を夫婦で500万円ずつに分散すれば、それぞれが低い税率を適用でき、世帯全体の手取りを増やすことができます。
青色申告特別控除
事業的規模の場合:最大65万円の控除が受けられます。(複式簿記での記帳、損益計算書・貸借対照表の添付、e-Taxによる申告が要件)
事業的規模でない場合:最大10万円の控除が受けられます。
純損失の繰り越し控除
不動産所得が赤字になった場合、その赤字を翌年以降3年間にわたって繰り越すことができます。これにより、将来の黒字所得と相殺して税金を減らすことが可能です。
減価償却費の活用
建物の取得費用を耐用年数にわたって経費として計上するもので、実際の支出を伴わない「みなし経費」である点が最大の特長です。これにより、手元の資金を減らすことなく、課税所得を圧縮し、税金を大幅に減らせます。
計算方法
個人の不動産所得の場合、減価償却費の計算には原則として定額法を用います。
減価償却費 = 取得価額 × 償却率
- 取得価額:不動産の購入代金(建物部分のみ)に、仲介手数料や登記費用などの付随費用を加えた金額。
- 償却率:建物の構造や築年数に応じて定められた法定耐用年数から算出されます。
新築と中古物件の減価償却
新築物件
法定耐用年数をそのまま使用します。例えば、木造住宅は22年、鉄筋コンクリート造は47年です。新築の場合、毎年一定額の減価償却費を長期にわたって計上します。
中古物件
築年数に応じて法定耐用年数を短く計算するため、短期間で多額の減価償却費を計上でき、高い節税効果が期待できます。これが、中古物件が不動産投資の節税策として人気が高い理由です。
耐用年数の計算(簡便法)
- 法定耐用年数の一部を経過した物件:(法定耐用年数−経過年数)+(経過年数×0.2)
- 法定耐用年数をすべて経過した物件:法定耐用年数×0.2
所得分散の活用
所得分散の活用方法を解説します。
累進課税の仕組みによる節税効果
所得税は 課税所得が大きくなるほど高い税率が適用される累進課税制度 です。
そこで、「不動産所得1,000万円を夫婦で500万円ずつに分散」した場合の節税対策を解説します。
1,000万円を1人で申告の場合 → 税率は33%のゾーンに突入
500万円ずつに分散の場合 → 税率は20%前後で止まる
つまり、同じ世帯合計所得でも「分けた方が低税率で課税される」 ため、全体の税額が下がります。
住民税の負担も軽減
住民税は一律10%程度ですが、こちらも課税所得に応じて計算されるため、分散することで「均等割+所得割」の計算が有利になります。
扶養控除・社会保険の調整効果
- 夫婦で所得分散すれば、配偶者控除を受けやすくなります。
- 社会保険(健康保険・年金)についても、夫婦でそれぞれ事業主報酬を受けることで、将来の年金受給額が分散されリスク分散につながります。
相続・贈与税対策にもつながる
夫婦でバランス良く所得を分散しておけば、資産形成も分散され、相続時の節税効果や分割のしやすさにもつながります。所得を1人に集中させると、将来的に相続財産も偏るため、相続税負担が重くなりがちです。
法人化による節税
不動産所得が大きくなり、個人の所得税率が高いと感じるようになったら、法人化を検討する価値があります。
税率の差
- 個人の所得税率は最大で45%(住民税を含めると55%)
- 法人の実効税率は、所得が800万円以下の部分は約15%、それを超える部分は約23%
| 区分 | 税率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資本金1億円以下の普通法人など | 年800万円以下の部分 | 下記以外の法人 | 15% | |||||
| 適用除外事業者 | 19% | |||||||
| 年800万円超の部分 | 23.2% | |||||||
| 上記以外の普通法人 | 上記以外の普通法人 | 23.2% | ||||||
所得の分散
不動産管理会社を設立し、家賃収入を会社に帰属させることで、個人の所得税率を抑えることができます。
経費の範囲拡大
会社設立費用や役員報酬、退職金なども経費として計上できます。
ただし、法人化には設立費用や社会保険料の負担、会計処理の複雑化といったデメリットもあります。専門家(税理士)に相談し、ご自身の収支状況や将来の計画に合わせて慎重に判断することが重要です。

不動産所得が 900万円以上になると、法人化のメリットが出やすくなります。法人なら経費計上できる範囲も広がり、生命保険料や退職金制度も活用可能です。
修繕費と資本的支出の使い分け
修繕費は一度に経費化が可能ですが、資本的支出は減価償却となります。
修繕費
建物を現状回復(貸出前の状態に復旧)するための工事 → 全額その年の経費にできる
資本的支出
建物の価値を高めたり(バリューアップ)耐用年数を延ばす工事 → 減価償却で按分
ローン利息や管理費の経費化
ローンの利息部分や管理委託費も経費に計上できるため、忘れずに処理することがポイントです。


家賃収入で相続・贈与対策


賃貸不動産が相続税対策になる理由
1億円を相続する場合、現金か不動産で相続した場合の評価額は大きく異なり、節税対策につながります。
- 現金 → 評価額そのまま1億円
- 自宅用不動産 → 評価額8,000万円程度
- 賃貸不動産 → 評価額6,000万円程度
路線価評価が時価より低い
相続税は「時価」ではなく「相続税評価額」で計算されます。
賃貸用不動産は、自用地よりも評価額が2〜3割低くなるケースが多いため、現金を持っているより節税効果が大きいです。
借家権割合の控除
賃貸中の建物は「借家権割合」が適用され、評価額がさらに下がります。
例)借家権割合30% → 建物評価 × (1 − 30%) で計算。
家賃収入による返済と資産形成
ローンを組んで物件を購入しても、家賃収入で返済すれば実質的に「他人資本」で資産形成できます。結果的に相続時の財産を効率よく増やしつつ、評価額を下げられるのです。
贈与税対策としての不動産活用
暦年贈与の活用
年間110万円までは非課税で贈与可能。現金ではなく不動産収入(家賃収入)を原資に少しずつ贈与することで、長期的に節税できます。
相続時精算課税制度
2,500万円までの贈与が非課税となり、将来の相続税で精算される制度。早期に子世代へ資産を移転したい場合に有効です。
不動産そのものの贈与
現金よりも「不動産」を贈与した方が、評価額が低いため贈与税が少なく済むケースが多いです。特に賃貸不動産は評価減効果が大きいです。
家族信託を活用した承継対策
高齢化に伴い、相続税対策だけでなく「認知症による資産凍結リスク」も重要になっています。
家族信託を利用すれば、オーナーが判断能力を失っても、あらかじめ指定した家族が不動産管理・家賃収入の受領を継続できます。
家賃収入に関する税務調査のポイントと注意点
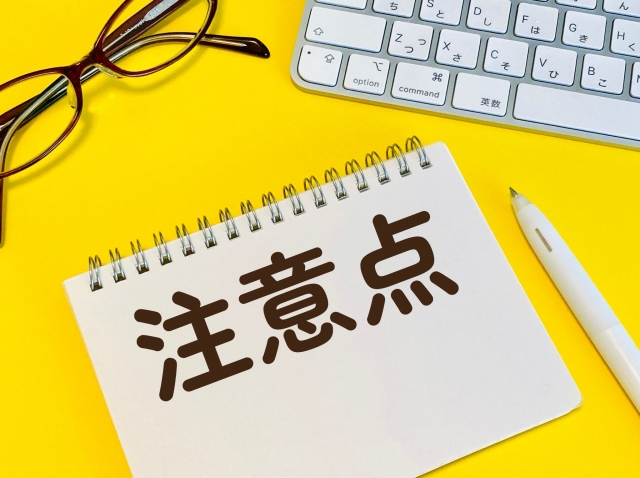
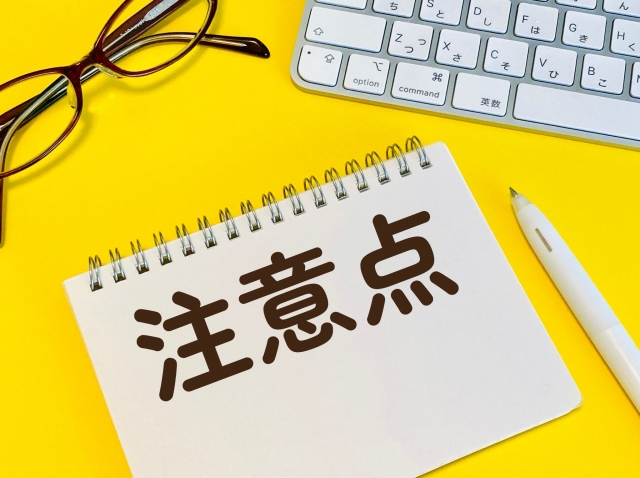
家賃収入を受け取り、不動産所得を申告する場合の税務調査のポイントと注意点を解説します。
税務調査が入るきっかけとは?
- 収入と経費のバランスが不自然(家賃収入に対して経費が極端に多い)
- 修繕費や広告費が一度に大きく計上されている
- 過去に確定申告をしていない、または遅延が多い
- 不動産売却益と賃貸収入を混同している
- 金融機関・入居者からの情報との突合で不一致がある
特に不動産は「登記」や「家賃の振込記録」で外部情報から容易に把握できるため、申告漏れはすぐに見抜かれます。
税務署がよくチェックするポイント
家賃収入の計上漏れ
- 礼金・更新料・敷引金(返還しない部分)を収入に入れていない
- 共益費を収入計上せずに経費と相殺している
- 駐車場代・看板設置料など副次的な収入を見落としている
経費の妥当性
- 修繕費と資本的支出の区別
→ 修繕費(経費計上可)と資本的支出(減価償却)が混同されやすい - 家族への給与
→ 青色専従者給与は「実際に労務を提供」「金額が妥当」でなければ否認される - ローン返済
→ 利息は経費になるが、元本返済分は経費にならない
領収書・帳簿の整合性
- 経費計上した領収書が保存されていない
- 帳簿と銀行口座の入出金が一致しない
個人利用との線引き
- 自宅の光熱費・通信費を賃貸経営の経費に含めている
- 車両費を全額経費にしている(実際は私用も含む)
注意点と対策
帳簿・領収書の保管
- 確定申告書の提出後 7年間は保管義務 あり
- 領収書は原本保存が原則だが、電子帳簿保存法を活用すればクラウド保管も可能
修繕費の扱い
- 「修繕費として処理 → 実は資本的支出」というケースは調査で最も多い指摘事項
- 工事内容・見積書・施工契約書を残しておくことが重要
家族給与の合理性
- 実際の労働時間や作業内容を記録しておく
- 相場に見合わない高額給与は否認されやすい
現金収入の扱い
- 店舗や駐車場で現金を受け取る場合、入金記録を必ず残す
- 税務署は銀行入金と現金出納帳の突合を重点的に見る
税務調査が来たときの心得
- 調査官は「不自然な部分を確認する」のが仕事。正しく処理していれば恐れる必要はない
- 記録や領収書を即座に提示できるようにしておく
- 対応が不安なら税理士に同席してもらう
まとめ
賃貸経営を行う上で、家賃収入に対する税金をいかに抑えられることが出来るかは非常に重要な戦略です。
正しい知識を持って、支出を抑えることが資産形成の最大化につながります。
これからご所有不動産を貸し出される方以外に、所得が増加している方や、相続・贈与を見据えた資産承継を検討されている方は、賃貸経営に強い専門家に相談することがオススメです。
クルーズカンパニーは賃貸経営の専門家として、収入を最大化し、各専門家との連携によって資産形成と防衛のサポートを行っております。
ご自宅の貸し出しや遊休不動産の活用についてはお気軽にご相談ください!
\賃貸経営のご相談は「クルーズカンパニー」へ/